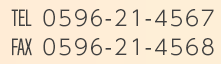企業向け研修 防災対策講座
備えておくと安心なこと、
知ってほしいこと、
そして、Action!
今後30年で、東海地震が発生する確率は約88%、東南海地震は70~80%、南海地震は50%といわれ推定される被害も甚大です。
さらに、過去の地震記録等によれば、これら3つの地震は将来連動して発生する可能性も高いとされています。
これまでの震災では、高齢者をはじめとする災害時要援護者の被害はとりわけ大きく避難をはじめ、避難生活におけるケアのあり方も問題とされました。
社会福祉施設は、入所者を災害から保護する義務があり、ふだんから、災害を想定した対策を準備しておく必要があります。
防災対策の更なる充実、強化を求めるため、この講座を一つの契機として、防災対策として何をすべきか、防災対策で十分であるか、少しでも被災をなくすためにはどうしたらよいかなどより有効な防災体制を図っていきましょう!
講座内容
(順序内容は時間によりいれかわります。)
2時間講座 例「防災ガイダンス基本編」
1、今、起こりうる災害を知る。過去の災害からの教訓。
2、今いる地域がどんな災害に弱いかを知る。ハザードマップの見方。
3、防災マップとは?
4、地震の瞬間いのちを守るためにどうしたらよいのかのレクチャー
5、命を守る日ごろの備え。毎日もちあるく防災グッズ。
工夫で災害に対処する知恵の伝授
6、災害時要援護者のための、「まちがえるための防災訓練」
7、避難後のコト
8、ふりかえり
2時間×2講座 例「防災と減災ワーク基本編」
第1回<講義>
1、こころのケアのためのワーク つながりつくりのワーク
2、地震や災害についてのレクチャー(過去の災害からの教訓)
3、今いる地域がどんな災害に弱いかを知る。ハザードマップの見方。
4、県内のいろんな地域での取り組み
5、防災グッズ、こんなものあります
6、 ふりかえり
第2回<実技>
1、ふりかえり&つながりつくりのワーク
(あなたは何ができる人ですか?)
2、地図上で、避難所の確認をしよう(福祉避難所の確認)
3、防災マップを作ろう
4、実際に歩いてみる(天候、開催場所により変更あり。その場合、
防災マップまとめ)
5、ふりかえり
※そのほか、避難生活でのワークとして
「防災ゲーム」をつかった講座もあります。
◆ 備品について
* 平机のようなテーブルを2つ、ご用意をお願いします。
防災グッズ等のサンプルを並べます。1つはグッズ回収用になります
* PCとスクリーンがご準備いただける場合は、
お願いいたします。
ホワイトボードの準備をお願いいたします。
* 地域のハザードマップをご用意ください(人数分)。
市町の窓口でもらえます。HPなどからダウンロードできます。
PCインターネットで、スクリーンに映し出せる状態だとありがたいです。
☆2回講座の場合の追加事項
* 参加者には入場の際、名札を作っていただきます。
ガムテープやシール(大き目の付箋でも可)などに
名前を書いてご参加いただきます。
マジックペンもご用意をお願いいたします。
*地域周辺の建物が載っている白地図(ゼンリンのコピーでけっこうです)
をご用意ください。
1ページずつコピーしたものを、講座の中でつなげる作業をしますので、
つなげなくても結構です。
畳半畳分くらい(A4ならば12枚。避難所までのっているもの)を
ご用意ください。
5~6人につき1セットでお願いいたします。
*作業に使います。
セロハンテープ、小さい丸いシール(付箋でもOK。3色ほど)、
サインペン(黒、赤、青、緑、オレンジ、ピンクなど5色ほど)、
5~6人につき1セットでお願いいたします。